ジョナス・メカスによる365日映画、12月24日、358日目。
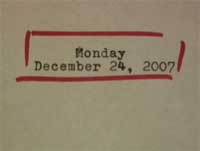

Day 358: Jonas Mekas
Monday, December 24th, 2007
20:07 min.
I celebrate my
birthday by telling
something about
myself ---
自分のことを
ちょっと語って
誕生日を祝う
ことにする
ジョナス・メカスは1922年12月23日生まれ。昨日が彼の誕生日である。
「自分のことをちょっと語る」とは27年前にセントポール(St. Paul)の友人サリー・ディクソン(Sally Dixon)の家の前で撮影された「自画像1980」(self portrait 1980)と題された映像のことである。
 (Sally Dixon)
(Sally Dixon)
サリー・ディクソンは60年代以来、スタン・ブラッカージュをはじめとする多くの映像作家と親交を持つ前衛映画専門のキュレータとして知られる。詳しくはこちら(Riding the (New) Wave: An Interview with Avant-Garde Film Curator Sally Dixon, January 2005)。
今日のフィルムは今までで最長の20分を超える長さである。
痩せて若々しいメカスは立ったままカメラに向かっている。撮影者は不明。カメラは三脚に固定されているようだ。時々ズーミングする。「今セントポール時間で午後2時15分前。2時5分には終わらせたいな」と前置きしてから、メカスは主に自分の名前、「映像日記」(Film Diary)としての自分の映画の特徴、新しい故郷(Home)としてのニューヨークについて語る。
季節は春の始め、5月4日だというのに、気温は華氏90度(90°F)だという。摂氏だとおよそ32.2°度(32.2℃)。余りに暑いので、冷えた缶ビールを飲みながらの撮影ということらしい。何度目かの「暑いよ(hot)」の後にすぐ「これは帽子(hat)。ニューヨークのあるストリートで見つけたんだ。私のキャラクター・ハットさ。」と続ける。
自分の名前の発音の仕方についてこう語る。「私の名はジョーナス。姓の綴りはエム、イー、ケイ、エイ、エス。ミカスと発音する人もいるし、メカスと発音する人もいる。リトアニアでの本来の発音はマカス。でもアメリカではメカスと呼ばれるようになったんだ。」
自分の映画の特徴についてはこう語る。「カメラの眼は嘘をつかない、と言う人もいる。私はと言えば、カメラの眼が本当に嘘をつかないかどうかは知らない。私の映画は非常に個人的、自伝的なもので、現実の生活をカメラで毎日記録して、いわば映画日記(Film Diary)を作るんだ。いうまでもなく、実際には編集を終えた一個一個のシーンは3、4分足らずで、人生のちっぽけな、ちっぽけな断片に過ぎない。人生の大部分は映画にならずに過ぎてゆく。でもそれらをつなげた映画日記は人生全体を凝縮したエッセンスとして表現するんだ。そんな映画もある意味ではフィクションかもしれない。でもその瞬間瞬間に強く感応して撮影したものから出来上がる映画は、時間的には人生のごく一部でしかないけど、私の人生の本質を表しうると思う。いや、分からないな、分からない……」
(追記)
いつの間にか、サリーがポーチに腰を下ろして一観客になっている。「さて、私はここに立っている。そしてサリーは、まだそこにいる。サリーは家から出てきてポーチにいる。ところで、これは、私が撮影されている。私は撮影していない。いつもは私は自分を撮影しない。私は映像の中にはいない。でも違いはないんだ。動画(moving images)としては同じだ。これは数ある道具の内のひとつさ。現実(reality)を記録して、後で再現したり、表現したりするためのね。私は映像の中にはいない。でもそれはそれほど重要なことじゃないんだ。他の媒体、例えば絵画でも同じだけど、人は必要に応じて道具を選ぶ。映像でも、フィルムを選んだり、コンピュータを選ぶことだってあるだろう。3G、ホログラムを選ぶことだってできる。私はずっとフィルムを選んで来た。なぜか自然に引き寄せられたんだ。そうしなければならなかった。ひとつの手段、道具としては、たしかに可能性は限られているだろう。ものすごく時間はかかるしね。」
ここでそばを横切る男を指さす。「リカルドだよ。リカルド・ボーク。」小型のカメラを手にしている。「小さいカメラだなあ」とメカス。「ところで、私は遥か遠くからやって来て、ここで成長した。そして今セントポールで映画(Cinema)について語っている(笑)。映画って何か、本当に分からない。映画は常に拡張しているし、どんどん枝分かれしている。言語が成長し、変化するようにね。ある日これこそが映画だと思っても、翌日誰かが映画を別の方向に動かすってことが起こるんだ。だから、いつも「始まり」(beginning)にいるんだ。自分自身を放り出してね。」
やや間があって、何か思いついたように「これが私の横顔(profile)」と言って、右横を向く。先ず右顔を見せて帽子を上げて下ろす、ゆっくり正面を向いて同じ動作を繰り返す。それから左を向き同じ動作を繰り返し、最後に背中を向けて同じ動作を繰り返す。サリーの笑い声が聞こえる。「これがひとつの私さ。本当に多くの私が実際に映画を作るんだ。多くの私のうちの一人が今ビールを飲んでいるってわけさ。分からないなあ。今のカシャって音はリカルドね。そういうわけで、友よ。ここに来たことは秘密なんだ。(ポーチの方を指差して)君たちといられて良かった。この暑い日にね。春。こうして君たちに語れるのは旅のお陰だ。」
「ここからどこへ行くの?どこへ発つの?」というリカルドか撮影者の質問の声が聞こえる。「私はどこへ行くかって?知りたくないなあ(笑)。ニューヨークに帰るよ。私の新しい故郷(My New Home)にね。私が立ち寄った(dropped)場所。私はニューヨークに来た(come)わけじゃない。立ち寄ったんだ。やむをえない事情でね。色んなことがあって私はニューヨークに立ち寄った。そして留まった。私は本来、旅や移動が好きじゃないんだ。1977年にリトアニアに叔父を訪ねたとき、叔父は言ったもんさ。われわれリトアニア人はみな地面に転がる石ころみないなもんだ。移動してきた連中に蹴飛ばされ続けてきた。上を通り過ぎる連中もいた。そんな石ころ(Stone)みたいなあり方。私はニューヨークに根を下ろした。強制的に故郷を追われる人がいる。選択したわけじゃない。私はよく言うんだ。砂漠の真ん中に私を落としてみろってね。そこで私は深く広く根を張ってみせるよ。すべてに愛着を覚えていた故郷を強制的に追い出された後、私はどんな場所にでも愛着を覚えるようになった。要するに、私は私に愛着がある(I attach myself.)。だから、どんな場所へ行っても平気さ。私は今正にここに愛着を覚えている。この場所(spot)にね。」
「そうだ、ちょっと撮ってみよう」と言ってメカスはカメラの背後に周り込み、ゆっくりとカメラをパンさせて、ポーチに腰を下ろしているサリーとリカルドの二人をフレームに収める。そして「君はどこにいる?」と歌うように言う。
メカスは「暑いな」と言ってからしばし沈黙の後、右手の方を指差す。「チューリップだ。撮ってくれ。花。花は現実だ。花は語らない。ところで、今は2時3分。残り時間は2、3分ってこと。皆、他に何を語ればいいと思う?」すると「世界創造プロセスの本性についての議論はどう思う?」とサリーの声。「そうか、世界創造過程の本性ね。(天を指差しながら)神がわれわれを創造した。時々不思議に思うよ。(溜息)もちろん、彼か彼女が(笑)。これは大きな疑問符だと思う。さて、ビールの最後の一滴を飲み干そう。」
帽子をゆっくり下ろして顔を覆い、カメラに接近するメカス。