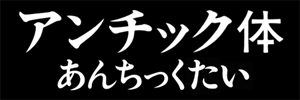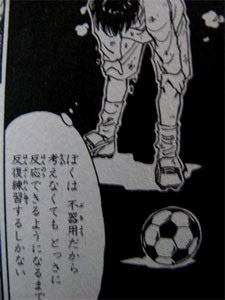カラス(crow)の羽毛か。それにしては色が薄い気がした。

ヒメリンゴ(姫林檎, Chinese crab apple, Malus prunifolia or Malus×cerasifera)。

ツララ遊び。こういうのを見かけると嬉しい。

トウモロコシ畑の雪上に謎の跡が。

カラス(crow)の雪浴び(snow-bathing?)の跡だった。風切り羽根の跡がくっきりと残っている。昨年末(2007-12-20)以来である。

独り雪だるま祭り、三日目。昨日の日中の暖気で大分雪が解けて、人相が変わった。角が短くなり、鼻と口が埋没し、眉毛がどこかに消えた。眉毛を調達した。
漫画の混植:アンチック体?
漫画で使用される書体に関しては「混植」(アンチゴチ)が一般的であると初めて知った。
現在の一般的な漫画雑誌や単行本では、漢字部分をゴシック体、かな部分を明朝体という書体とした混植が一般的である(これをアンチゴチという)。*2
え?「アンチ」ってまさか「反」じゃないよな、何だろう?と思って調べたら、「アンチック体」のことだった。アンチック体とゴシック体の混植というわけだった。
この書体は、書体の種類が乏しかった戦前に生まれました。元々は金属活字のゴシック体(漢字)に合わせてデザインされたとされる肉太な仮名文字で、これがアンチック体の源流です。その時期は現在のゴシック体の仮名のデザインに落ち着くまでに試行錯誤が行われていたようです。金属活字で文字が組まれるのが一般的だった昭和前半までの印刷物に、ゴシック体+アンチック体の混ぜ組みを見ることができます。写研のものは写植最古のアンチック体で、1935年に誕生しました。
写植の書体数が今より少なかった1970年代前半あたりまでは、特太明朝体の仮名をアンチック体に組み替えてより力強い表現を求めることもありましたが、現在では漫画の吹き出しに使われるのが殆どです。漫画の吹き出しに使われる書体は、かつては明朝体が主流でしたが、1960年代には現在のような「石井太ゴシック体+中見出しアンチック」(いずれも写研)が定番になりました。このスタイルが定着した理由は不明ですが、吹き出しの周りの絵に負けない“黒さ”と、筆書きに忠実であまり主張しない字面がどんな絵柄にも溶け込むからなのではないかと思います。
「へーっ、そうなんだ」と思って、子供部屋にあった樋口大輔著『ホイッスル!Number.1』(集英社、1998年)で確認してみたら、基本的には確かにそうだった。
もちろん、実際には内心の声は細い明朝体が使われたり、叫び声には太い丸ゴシック体が使われたり、オノマトペには手書き文字が使われたりと、多彩な活字の組版になっている。他人事だが、漫画の組版はかなり大変な、気の遠くなるような作業のような気がする。案の定、以下のような記事が少なからずある。
この記事のなかに、清水直紀氏(共同印刷出版情報事業部営業企画部部長)が、マンガの制作現場でデジタル化が遅れている二つの理由について語るところがある。
「いまだに、紙ベースの画稿が主流であることが理由の一つに挙げられます。従来どおり手描きスタイルのマンガ作家が多いため、我々の手元に届く画稿の8割が紙ベースとなっており、残り2割がようやくデータ化された状況です」
もう一つの大きな理由は、マンガ独特の組版や文字表現にあると言う。「マンガは一見、単純にできているように見えますが、形や大きさが異なる吹き出しの中にきっちりと文字を組まなければなりません。また、漢字すべてにルビをふる“総ルビ”のほか、通常の出版物では使わないような文字表現、たとえば、『あ』に『 ゛』や『お』に『 ゛』、ビックリマークが4つ並ぶ『!!!!』といった独特の表現を多用するため、デジタル環境での作業は複雑で手間も時間もかかります」
なるほど。それは大変だ。
昨日(2008/02/09)、takuoさんから教えられた「修悦体」の誕生が活字のひとつの「前衛」だとするなら、漫画の印刷の世界にもうひとつの「前衛」があるような気がした。
ところで、漫画家は自作漫画の書体を自由に選定、指定することはできるのだろうか。私が昔本を出したときには編集者まかせで一切口出しはできなかった。詩集では、アメリカのある詩人が例えばオプティマ (Optima)で組むことを指定して、その仕上がりに喜んだという話を聞いたことがあるが。
なお、『日本語練習中』に漫画の「ふきだし」への注目から、アンチゴチのルーツを探る渋く興味深い記事がある。
活字の源流から未来の書物へ

これは祖父の形見の印鑑のひとつ。初めて見たときはなんて小さいのだろうと驚いたが、隣のマッチ棒の断面よりもずっと小さな面に文字をしかも鏡文字を彫刻してきたのがいわゆる活字地金彫刻師たちである。
一昨年にプライベートプレスの私家活版印刷所『海岸印刷』を始めた橋目侑季さんは、「日誌」のなかで清水金之助氏(1922- )による活字地金彫刻の実演見学会に参加なさったときの貴重な体験を美しい写真とともに瑞々しく綴っている。
活字地金彫刻は合金の軸に直に文字を彫り込んで種字を作る技術のこと。
活字の元となる型が母型で、その母型の元となるのが種字。まさしく活字の元の元。
(中略)
この日感じたことはなんとも上手く言い表しがたい。活字の源流を目の当たりにしたということ。
清水さんの技術。人柄。種字の美しさ。人間の手の可能性。
あるいは「活字」というと(「活字になる」という表現があるように)
「手書き」の対極の響きがあるが、その活字もまたかつては源から
人間の手仕事により生み出されていたということ。その重み。
先日紹介した活版工房(LUFTKATZE)の平川さんもブログ活版散歩で同じ見学会の模様を報告なさっている。
平川さんによれば、
清水さんが彫っているものは、電胎母型(ガラ母型)の種となるもの。
母型を作るための種字を活字合金に逆文字を直接小刃で彫っていくのを「地金彫刻」と言います。彫られた物から母型ができるのは5回くらいまでだそうです。その母型からは何万もの活字が生まれて行きます。
というわけで、地金彫刻はまさしく活字の生命創造作業に他ならない。
橋目さんと平川さんの報告を読みながら、約半年前に港千尋『文字の母たち』(asin:4900997161)で、大日本印刷活版部門の最後の職人、彫刻師として活躍した中川原勝雄さんの「直彫り」ないし「新刻」の実演を目の当たりにしたときの驚きを綴った章「直彫りの驚異」に動かされて書いたエントリーのことを思い出していた。
そして急いでつけ加えなければならないことは、港千尋氏の眼差しは単に過去に向けられているだけでなく、世界中の書物の頁が文字単位でデジタル情報化されてインターネット上を流通するであろう近い未来にも照準しているように読めたことである。
字を彫る人の姿勢は、ルーペを使っているとはいえ、基本的には字を読む人の姿勢と同じである。彼や彼女は椅子に座り、小さな字を見つめる。そのとき字を彫る身体は、本を読む身体と同じ知覚をもっている。字を彫ることは書物のアルファであり、印刷された字を読むことは書物のオメガであるが、その最初と最後がひとつにつながるように、同じ身体によって担われていることが、重要なのである。
その身体感覚は、おそらくデジタルの時代にこそ求められるものだろう。文字を作り出すことと読むことを結びつけ、書物のアルファとオメガをつなげるためには、これまで人間の手によって彫りだされてきた、すべての文字が必要になるだろう。それらの母型をとおして立ち上がる記憶は、未来の書物の血肉となるであろう。
(『文字の母たち』084頁)
ところで、来る3月8日(土)に、平川さんらが企画、主催する「活版印刷を知る勉強会」にて、清水金之助さんをお迎えし、実演を交えながらお話を伺うことができるという。詳細はこちらで。
ちなみに、一昨年の「第13回東京国際ブックフェア2006」に関する記事が思いがけず示唆的だった。
というのは、その中で偶然に、大日本印刷が「ものづくりの原点」と位置づける活版印刷の活字の直彫りを実演展示し、大勢の観客が見守るなか、中川原勝雄さんが一心に彫り続ける様子と並んで、ムサシの出品した米国キルタス社(Kirtas Technologies, Inc.)製の自動ブックスキャナが紹介されていたからである*1。つまり、いずれは朽ち果て消えていく物質的記憶は、電子的記憶として継承されていくことになるだろうという示唆である。
*1:Kirtas社のスキャナーに関しては、かつてbookscanner記で取り上げられたことがある。「自動車」における「自動」の意味(2006-11-17)参照。