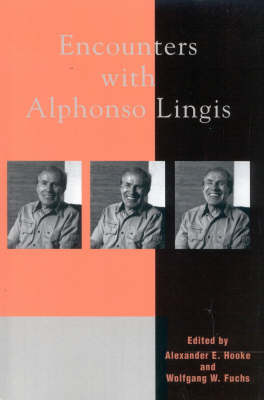アルフォンソ・リンギスの素顔とインタビューはこちらで。
アルフォンソ・リンギスの声はこちらで。
***
アルフォンソ・リンギスに関するエントリからの抜粋。全文はリンク先で。
もちろん、今日の世界でわれわれは国籍をさっさと離脱するわけにはゆかないし、国家によってしばられあるいは守られ、国家単位の社会の中になんらかのかたちで住みこむという生き方を捨てることもできない。しかしそうした国家主義+国際主義の世界に重ね描きされた、突発的な出会いと葛藤の現実を、われわれの多くはいたるところで実際に生きている。
私はリンギスを「旅する思想家」とか「旅する哲学者」というキャッチフレーズで賞揚することに違和感を覚えている。また、リンギスが「哲学者」であることを否定しようとする傾向にも疑問を持っている。リンギスのように「旅する」ことが問題ではないし、リンギスはまぎれもなく類い稀な哲学者だと思う。一見読み易いからといって、理解し易いとはかぎらない。翻訳したからといって、理解が十分とは限らない。
他人の旅の経験の記録、travelogueを読んで感動することは、それ自体の意義とは別に、日常の経験を具体的に変えることへと繋げられなければ、それこそ狭義の「知識」に終わってしまいかねない。リンギスの旅の経験の記録の仕方から、私は私の日常を本質的な「旅」として記録、記憶しながら生きることを学ばなければ、リンギスを読むことの意義は半減してしまうと思っている。リンギスの本が哲学の書棚に置かれようがどこに置かれようが、そんなことはどうでもいいことである。
昨日ちょっとだけ紹介したアルフォンソ・リンギスは、私が知ったつもりになっていた世界に非常に思いがけないリンクをたくさん張っていて注目するようになった。例えば、昨日一部引用した『信頼』では、私が分かり切っていると高を括っていた「信頼」について、「勇気」だけならまだしも、「笑い」、「性的渇望」、「性的魅惑」、「エロス」までをも説得力豊かに結びつける。
つまり「信頼」とはいつも危険や死と隣り合わせの、しかしそうであるが故にエロティックでさえある飛躍なのだ。
しかも、である。リンギスの「信頼論」は「憎悪論」とも分ちがたく結びついている。
私の理解では、本書『信頼』96頁から99頁に凝縮されて書かれている「憎悪論」あっての「信頼論」である。リンギスによれば、憎しみは容易に「一般的で名もないだれか」、「他人ども」、抽象的な他者への憎しみへと増幅されていく。対する信頼は具体的な個人、「きみ、あなた」に触れる。憎しみの本質はその抽象性にあり、人間の抽象性によって成り立つ社会は常にその温床であり続ける。信頼の本質はその具体性にあり、人間の具体性が社会性を破って露出する場面においてよく機能し出す。「旅」とは人間を社会的抽象性から人間の具体へと連れ戻す体験である。しかし、読者としての私たちはその「旅的具体性」を日常生活にどのように接続していったらいいのか。本書を大きな喜びととに読んで終わり、でいいはずがない。
その方法ははっきりしている。日常を「旅化」するしかない。そもそも「詩人」であるとは、日常の旅人であることではなかったか。
自然が造形する色と形の妙技に限りなく近づこうとした芸術には何があるだろうか。あるいは、自然の実在に接近しようとした言葉の技には何があるだろうかと考えていた。ル・クレジオのエセーやアルフォンソ・リンギスのトラベローグはそれに近いかもしれないと思い当たった。植物や青空や雲の実在に触れるような言葉。実在との距離そのものを深く自覚した言葉の使い方。
旅の哲学者と異名をとり、その文体は書斎の肘掛け椅子から限りなく遠い未知の異国の風土の光や土や風の臭いを運んで来てくれる等と賞讃されることの多いアルフォンソ・リンギスの著作。しかし、そうだろうか。たとえそうだとしても、そんなことを有り難がる人間などどこにどれだけいるだろうか。多くの人間が今生きている場所で四苦八苦しているのだ。異国の異質な風土のテイストなど何ほどのことか。
語る内容ではなく、語ること自体が重要になる極限状況(死に行く人を看取る場面など)が真のコミュニケーションが始まる地点、すなわち人間にとっての最も根源的な絆の在処(ありか)を示すのだというリンギスの主張についても軽く触れたことまで思い出して、読み返していた。
その頃、人間たちは死を共有することはできないが、同じように死に条件づけられていることによって、「何も共有していない者たちの共同体」を構成するのだ、と理解していたような気がする。今も思想的にはそのあたりをうろうろしている自分がいる。
「個人」を身体の最も深いところで捉まえたい、そして個人がある意味でその固有の身体を超える瞬間の意味を捉まえたいという関心から色んなものを読みあさっていて、アルフォンソ・リンギスの『異邦の身体』のなかのある箇所に立ち止まっていました。