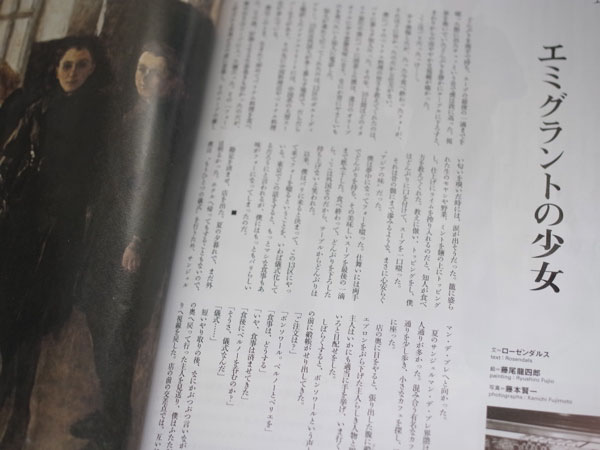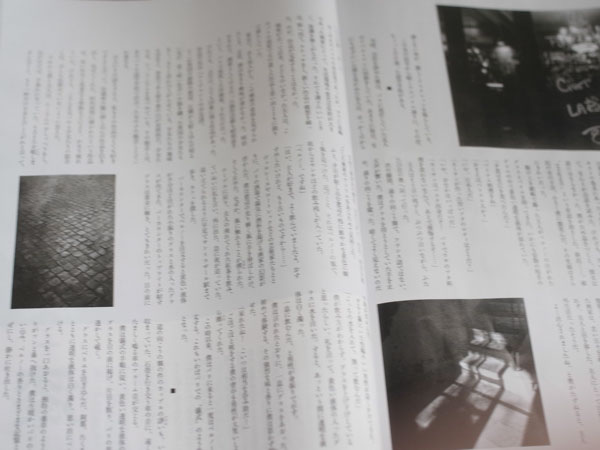21日朝、東京に戻り、最後の用事を終えた。帰りの飛行機に乗るまでに映画を1本観られるくらいの時間が残っていた。というのは、札幌を発つ前に、18日から「ゴダール・ソシアリスム」が公開されることを知り、もし時間がとれれば、観ようと思っていたのである。馴れない電車を乗り継ぎ、日比谷のTOHOシネマズシャンテに向かった。有楽コンコース(*URA*U CONCOURSE)の欠けた二文字は二年前のままだった。映画館の柔らかいシートに体を沈めた途端、眠気に襲われた。半睡状態で、夢でも見るように映画を観た。「ゴダール・ソシアリスム」は完全な眠りを妨げる力に漲っていたように思う。
羽田を飛び立った飛行機のなかでANAの機内誌をぱらぱらとめくっていて、パリで亡くなった画家、藤尾龍四郎の一枚の絵をめぐる旅の記憶を綴ったローゼンダルスの「エミグラントの少女」と題した文章が目にとまった。藤本賢一撮影のサイズがまちまちのモノクロームの写真四枚とそれらの波打つレイアウトに目をひかれたのかもしれなかった。文章のなかに、旅の終わりに「僕」が独りで執り行う「儀式」の話が出てくる。それは旅の思い出や記憶を葬るような儀式である。
僕は儀式の手順に従い、黄色い透明な液体の入ったグラスを目の前に掲げ、片目を瞑り、パリの思い出を透かして覗く。
グラスにペリエを注ぎ込んだ、刹那、たくさんの泡とともに透明な液体は白く濁り、思い出にベールをかける。
グラスを一口あおると、独特の薬草のような強い香りがツンと鼻に抜けた。僕は生暖かいパリの夜気を吸い込み、ペルノーの香りとさまざまな記憶とを綯い交ぜにし、静かに吐き出した。ANA December 2010, 127頁
ペリエで割ったペルノーが飲みたくなったが、機内ではペルノーもペリエも手に入らない。かわりに、和歌山産の生姜をたっぷり使った純粋なジャンジャーエールを三百円で買った。旨かった。生姜のエッセンスが胃袋をチクチクと刺激する。まるで今回の旅の思い出や記憶が胃壁に生姜の繊維で縫い込まれていくような気がした。私にとってはこの方が「儀式」としてふさわしい。それにゴダールの映画を観たことも私にとっては旅の終わりの「儀式」のようなものだったのかもしれない。飛行機が着陸態勢に入る直前、スチュワーデスが窓の外に皆既月食が見られるとアナウンスした。機内が反映する窓を覗き込んだ。目を凝らすと、それらしき発光体をなんとか確認することができた。