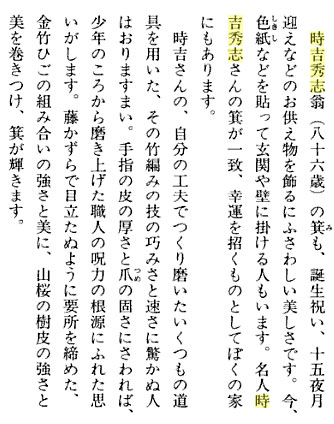- 作者: 沖浦和光
- 出版社/メーカー: 岩波書店
- 発売日: 1991/09/20
- メディア: 新書
- 購入: 3人 クリック: 7回
- この商品を含むブログ (14件) を見る
本書には後述するように隼人の末裔かつ竹細工師である一人の翁の北海道のタコ部屋とアイヌ部落に関する意外な想い出話が綴られている。それに触れる前に本書の狙いと眼目を確認しておく。本書は学問的には、日本列島の基層文化あるいは日本文化の深層に連なる一つの水脈を、日本人の民族的源流の一つである南島系海民の民俗と文化を射程にいれて、とくに南島文化と隼人との関わりに注目しながら、〈竹の民俗〉に探ったものである。しかしながら、そこにはより人間的な課題が孕まれていた。それについて沖浦和光は次のように述べている。
私はこれまでに数多くの被差別部落を訪れて、そこに伝わる民俗・宗教・産業技術などについて調べてきた。訪れるたびに、古老たちに部落に伝わる伝承や昔話、それに想い出話や苦労話を聞かせてもらった。差別と貧困とたたかいながらこの世を生き抜いてきた古老たちのとの出会いは、私の人間観に大きい衝撃をあたえた。なんとか生きていくための必死の人生から学んだ知恵と、厚い義理人情を身につけた古老が多い。底辺という視座からは、人の世の冷たさ、あたたかさ−−すべてのものがよく見えるのだ。
その生涯についての語りには、「人間とは何か」「人間いかに生きるべきか」という問題について、根本から問いかける何ものかがあった。そこには、書物から読み取るだけの表層の歴史記述からは到底得られない、この〈人の世〉の深層に関わる何ものかがあった。そのような古老たちとの出会いから多くのことを教えられたが、この『竹の民俗誌』もその所産の一つである。(「あとがき」243頁)
末期の眼にもつながる「底辺という視座」は大変興味のあるところである。本書の後半には、そのような古老の一人、「現代の竹取翁」とも言うべき時吉秀志(ときよしひでし)翁が登場する。
沖浦和光は1989年に部落と竹器生産との歴史的な関わりについて調べるために、阿多隼人の故郷である薩摩半島阿多を訪れた際に(薩摩半島は日本一の竹の産地であるとともに、竹細工の発祥地であるといわれる)、偶然時吉秀志翁に出会ったという。時吉秀志さんは阿多の部落に生まれ育ち(阿多隼人の末裔!)、苛酷な差別を生き抜いてきた当時七十八歳の現役の竹細工師であった。
明治維新後に、阿多の部落ではその由緒ある地名を変えた。自分の姓を変えた人も多かったという。時吉という姓は薩摩の数多い部落の中でもよく知られた姓であった。しかし、時吉さんは姓を変えず、その昔島津勢と戦った由緒ある古い家名を守ってきた。「われわれの先祖がなにも恥ずべきことをやってきたのではない、最底辺の民とされてきたが、なくてはならぬ仕事や技術の担い手として頑張ってきたのではないか。責められるべきは差別を強制した権力の側にある」というはっきりした思想を持つ時吉秀志さんは、沖浦に差別と竹細工との関わりについて率直に教えてくれたという(202頁〜203頁)。
時吉翁は竹細工師としての仕事と技術について沖浦に次のように語ったという。
この歳になっても、自分で山に入って、良いキンチク(ホウライチク)を探す。それにサクラの皮とフジカズラ、ヤマビワとツヅラを採る。ツヅラ採取は秋の彼岸から霜がおり始めるまでだ。箕の底にヤマザクラの皮を入れるのはこの地の伝統技術だ。
フジカズラは、石の上で叩いて柔らかくして、その内皮をとって陰干しする。幅三ミリほどに細長く割いた竹ヘギをヨコに、サクラの皮とフジカズラの繊維をタテにして編んでいく。ヤマビワの木を曲げて縁にし、最後にツヅラで締めて仕上げる。すべて自然からいただいた天然の素材で出来ている。まあ、この道具を見られたら分かるように、十種類を使うがすべて先祖伝来の手作りである。誰が考え出したのか分からないけれど、私たちのやっている箕作りは、たぶん何百年、何千年も前からずっと受け継がれてきた細工だろう。
このサクラの皮にしても、海からの潮風にあたった樹齢十数年のヤマザクラが一番良い。フジカズラも赤味の色でシワがよった物が上等だ。どこの山のどこに良いものがあるか、いつも山中を歩き回っているのでよく分かっている。一週間に二回は、この愛犬を連れて道のない急坂をよじ登りながら採取してくる。山に入るときは一日仕事だ。(205頁〜206頁)
古代から最も重要な竹器とされた「箕」は、やはり今日でも薩摩半島が最高の産地であることが窺える話である。
時吉翁がそれまでの波瀾万丈の人生を振り返って淡々と語った中で、北海道のタコ部屋とアイヌ部落の想い出話が飛び出して、吃驚した。
子供の時から、親父のそばで見様見真似で竹細工を覚えた。精神統一が一番大事だ、雑念が少しでも頭に残っていると箕の編み方が崩れてしまうと、父からきびしく叩き込まれた。だが、狭い仕事場に座ってずっと一生竹細工をやらねばならないと思うと、だんだん辛抱できなくなってきた。貧しい家計を助けねばならず、小学校へもまともに行っていないので、これという目当てがあったわけではないが、やはりなんとかして世に出たいという少年の夢があった。
それでとうとう十六歳で家を出て、大阪で沖仲仕をやったが、少年にはとても重労働だった。いろんな仕事をやったが、二二歳の頃には北海道のタコ部屋へ入って、ダイナマイトを使う危険な仕事をしていた。ところが、六カ月後の契約期間が切れても帰してくれないので、顔見知りだった近くのアイヌ部落に逃げ込んだ。とても親切で義理に厚い人たちだった。そこに十七歳の可愛い娘がいたが、あのままそこに一生いた方がよかったのではないかと懐かしく思い出す。そのことを今でも寝物語に言うものだから、そのたびに老妻と喧嘩になる。
戦争中は九州の有名な親分が組織した土方軍団に入っていた。大きな「出入り」があると聞いて駆けつけたら、なんと戦争だった。いまさらイヤとは言えず、五年間も戦場を転々とした。中国大陸からラバウルへ、さらにガダルカナルに飛び立つ飛行場設営隊として熱帯の島々を転戦した。その軍団の料理方をやっていたが、もうこれでダメだと覚悟した時が何回かあった。
戦争が終わって、命からがら故郷に帰りついた。再び箕作りに専念するようになった。戦後すぐは、箕は飛ぶように売れた。農家はもちろん、どこの家でも祭礼の時などにも神様への供物は箕に載せるのでよく売れた。一週間も寝ないで作り続けた時期があった。(205頁)
まさか、「北海道のタコ部屋」や「アイヌ部落」が出てくるとは思いも寄らなかったが、さもありなん。本書の主題と問題からは逸れるが、隼人とアイヌとの邂逅は、深い縁、歴史の細い細い糸のつながりを想像させ、また部落が一種のアジールとして機能したこともあることを窺わせて、大変興味深い。
参照
- 作者: 和真一郎
- 出版社/メーカー: 南方新社
- 発売日: 2005/12
- メディア: 単行本
- クリック: 4回
- この商品を含むブログ (1件) を見る
奄美ほこらしゃ(Google ブックス)