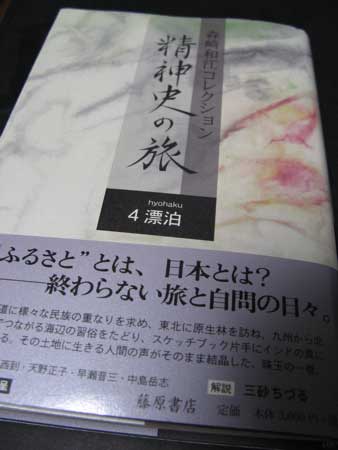人は一生に何度「生まれる」のだろうか?
森崎和江さんは子育てが終わった頃に「ふたたび旅へ」(1976年)という非常に印象的な文章を書いている。若い頃には人は二度生まれるものと感じていた、という。すなわち、人は一度は母の胎内から生まれ、やがて思春期にみずからの決意で生まれる、と。だが、いわゆる子育てが終わり、子どもたちが巣立った後の一瞬の空白の時間の中で、住み慣れた古巣はまだ彼らに必要かもしれぬという親の感傷とは裏腹に、これから再び自分がみずからの決意で「生まれる」という強い予感に襲われる。
が、どうやら人の人生は二度に終わるものではないらしい。かつて芭蕉が心のおもむくままに、肉親を捨て故郷を捨てて旅立ったのを知ったとき、まだ若かったわたしは、かすかな侮蔑さえにじませながら、その孤高な精神をしらじらしく見送った。が、いまにして思うのは、それは二度の生誕で終わることのない人の、やむをえない歩みにすぎなかった。
青春の旅立ちのはなばなしさに比して、人生をのぼりきった者の、あらたな出発はひそやかである。芭蕉ならずとも、やむにやまれぬ鬼神につきうごかされて、四十年五十年の座り心地を惜しげもなく捨てて、さらになにかを追い求めて旅立つ人も、きっと少なくないことだろう。いや、あるいは多くの人びとが、若さに別れを告げ、老いを手近に引きよせるとき、青春に味わったあの身ぶるいするような、未見への期待に緊張するのかもしれない。そしてそれは、蝶になろうとするいのちのぬれたかがやきのような、あらなたいのちへの化身であるにちがいない。
それにしても、その旅立ちはこのように心にときめきを起こさせ、捨てるものへの愛情に涙ぐませ、しかもまだ手にふれぬくらやみを恋うようにせつないものなのか。もはや二度目の生誕の折のように、みごもることや、身ふたつにわかれることや、名を成すことへの願望とはちがって、化身の果ては蛇が出るか鬼が出るか、まるで知りようがないおそればかりがただよう。わたしをいざなう。わたしのつばさが、ひくひくとけいれんするのである。とび立とうとして。(中略)
親となったわたしは、おまえたちが生まれてくれたおかげで、たくさんのことを味わうことができた。おまえたちと生きてきたおかげで、二倍も三倍も生きた。その細い道が、火の色をしてつづいている。
けれどもこの世はたいそうひろくて、それは蛍の道のようだ。
わたしを呼ぶ声がしきりにする。まるで蝶の季節に、うすい羽根がくさむらでうごめくように、わたしのなにかがこたえてしまう。そして、わたしはぼんやりしながら考える。精神の系譜のごときものを。
ひとところに根づけぬもの。心あこがれて旅立つもの。流転によってみのるもの。それら流れ者の文明をしっかと握った者たちが、この世には脈々と生きていたのではあるまいか。わたしたちのふるさとは、永久不変の土着性にとどまらず、あたかも風の変化(へんげ)のごとく、住みなれた境地からまだ身に染まぬ荒れ地へと、冒険してしまう精神たちのなかにもひろがっているのではあるまいか。
そしてわたしは、どうやらその流れ者の系譜につながるらしい。芭蕉とひとつ屋根に寝たうかれ女(め)のように、どことも知れず歩きながら、この人の世に涙をそそぎたがる。いま生まれくるもの、いま死にゆくもの、いま争うものへと、心に色香が立ちまよう。とび立てば、空は、やみというのに。森崎和江「ふたたび旅へ」、『精神史の旅 4漂泊』所収、174頁〜176頁)
「五十、六十は洟たれ小僧、……」や「人は土地に根づくのではなく、種(たね)に根づく」という周防大島に昔から伝わる言葉、そして「五十、六十が蕾なら 七十、八十は花盛り……」というナミイおばあの唄も聞こえてくる。